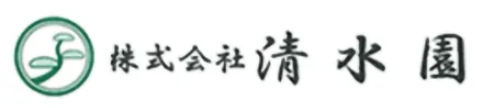vol.129 花展
2025/9/15
皆様こんにちは。清水園でございます。
今回のコラムでは、「花展」についてお話させていただきます。
代表は以前から習い事で生け花を続けていましたが、当初は花展や他の人の作品に対してあまり関心がなかったそうです。しかし、師事している先生から「発表することの大切さ」を説かれ、気がつけば何度か出展する機会に恵まれました。
代表が通うのは一般的な教室ではなく、マンツーマンの個人稽古のため、花展に出るまでは他の生徒さんたちと接することが全くなかった為、どんな作品を生け、どのような考えを持っているのかを知る機会がなかったといいます。
「花展に出るまでは先生が用意してくださったお花を何の疑問も持たず生けていただけで、お花屋さんに足を運ぶこともなく、どんな花材を集めてどんな作品に仕上げるのかを考えたことすらなかったと、改めて気づかされました」
「初めての花展の後は、なんとなくお花屋さんにも通うようになり、お花と真剣に向き合えるように少しずつなりました。今となれば花展を勧めてくださった先生には、とても感謝しています」
はじめての花展当日は、先生の付き添いがない中での出展となりましたが、代表は堂々と、らしさのにじむ所作で作品を仕上げたそうです。本来であれば「門標(いけばなの指導ができる資格の証)」を持つ者は「生花」を生けるべきとされる中、先生の指導のもと「自由花」での出展をしてしまったため、会場が少しざわついた場面もあったようです。
その後、先生が突然亡くなり、先生の遺言のおかげで新しい先生に拾っていただき、しばらくはお稽古のみを続けていましたが、再び先生から花展のお誘いがあり、出展することになりました。今回は流木を使った花器に「自由に生けてよい」とのことで、ありきたりな木の枝を使った素朴な作品を制作したところ、大きな注目を集めたそうです。多くの来場者が興味深そうに写真を撮っていたとのことでした。
「私自身、この作品は造園屋らしさが出ていてとても気に入っています。山の風景を切り取ったようなイメージで仕上げました。」
「作品のポイントとしては、流木の隙間から苔が生えているような雰囲気を演出し、堅苦しさを和らげる構成にしました。お花も絶妙なバランスで挿していて、自分なりに納得のいく仕上がりでした。」
花展では、技巧を凝らしたり、枝をスプレーで加工したような個性的な作品も多く見られる中で、代表の作品は独自の視点と発想が際立ち、先生からも「なかなか思いつかないアイデアだった」と高評価を受けたそうです。
華道とは異なりますが、日々、造園業を通じて美的感覚と技術を磨き続けている代表ならではの感性が、お花の世界にも表れているのだと感じます。
また、昨年の花展では連続での出展となり、「これまでにない花展にしたいので、映える作品を」との通達を本部から受けたそうです。
今回は、ガラスのカクテルグラスに作品を生け、下からライトアップする展示方法での出展となりました。代表は、お花そのものよりも「光の透過率」にこだわり、会場で作品づくりに約3時間を費やしました。サブの作品にハートモチーフを取り入れた、可愛らしさのある作品となり、来場者がこぞって写真を撮っていたそうです。
「花展では、同じ流派の中でもさまざまな技術を持つ人たちが集まってくるので、良い作品から学ぶことができたり、自分の作品に対する評価を聞けたりと、興味深く感じることも多いです。」
「また、空間構成力や色のバランスを考える力は、造園業にも通じるものであり、お花を学んできて本当に良かったと思います。お花の世界では“無駄を削ぎ落とす”という考え方が根底にありますが、その精神は日本の芸術全般、そして造園にも共通していると感じます。ただ、レベルの差によって、私の見ている景色と先生が見ている景色はまったく違うのだと、自身の力のなさを痛感することもあります。」
どの業界や職種においても、ある「ライン」に立たなければ見えてこない景色があるのだと、代表の花展を通して改めて考えさせられました。見たい景色に辿りつくためには、日々努力し、考え続けることが大切なのだと思います。
今後の代表の花展での活躍にも、ますます期待が高まります。
次回のコラムも、どうぞお楽しみに。