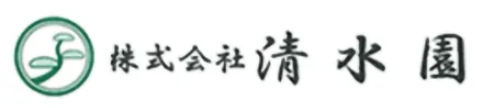vol.128 垣根工【後編】
2025/9/1

― 後編 ― できる庭師であるために ― 垣根づくりが教えてくれること
続いて、別の施工主様宅で行った垣根の作り替えについてご紹介いたします。
こちらのお宅には、格子垣・玉垣・四目垣の3種類の垣根があり、天然の竹で作り替えたいというご要望をいただきました。
もともとは別の造園業者が剪定を担当されていたのですが、垣根の作り替えは難しいとのことで、清水園にご依頼いただきました。
お客様から原型のない状態でご依頼いただくことも多く、その際は、もとの形を想像しながら制作を進めていきます。
竹は「籾殻(もみがら)」で擦って磨きますが、近年は籾殻の入手が難しくなっています。見た目がきれいな竹でも、意外と汚れているため、丁寧に磨くことで美しさが際立ちます。
市販の「激落ちくん」などで代用されることもありますが、早く磨ける分また磨きすぎて傷が付くため、竹が白くなってしまうので、一長一短です。
その後、柱を立て、竹の胴縁(どうぶち)のバランスを取りつつ、洋風の花壇に合うように調整しながら仕上げました。
今回のように、伝統的な垣根をしっかりと作る機会はなかなか得られるものではなく、とても貴重な経験となりました。
日本の文化として受け継がれてきた技術を、これからも守っていきたいと考えていますが、実際に経験できる場が限られているのが現実です。
ただし、竹垣の仕事が舞い込んだときに「今から勉強します。やらせてください。」では遅く、「できますよ」と言える人間であるべきだと、日々準備を重ねています。
現代は情報があふれ、学ぶ手段も多様に存在しています。「やったことがない」「教わっていない」というのは、できないことの言い訳に過ぎません。
やらない理由はない。だからこそ、常に意識的に学ぶ姿勢が求められるのだと、強く感じています。