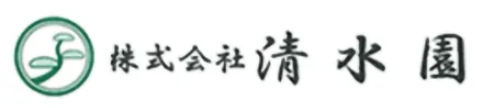vol.127 令和6年度 日本庭園管理士補ステップアップ研修【後編】
2025/8/4

ー 後編 ー 令和6年度 日本庭園管理士補ステップアップ研修 〜現場で得た気づきと学び
今回の研修で、代表が最も苦心したのが「待合」の基礎づくりにおける“レベル出し”の作業です。
地盤のどの高さを基準に整地を行うかを決める作業で、これを誤ると、最終的に石が地面に沈みすぎたり、逆に浮き上がってしまう原因になります。
今回の現場では、約12センチの勾配があり、どこで平均をとるかを慎重に見極める必要がありました。さらに、講習会ということもあり、図面がその場で手渡される“ぶっつけ本番”の状況だったため、普段のような事前準備ができない分、現場での即断力が試されました。
また、「うろこ垣」の制作にも苦労がありました。今回使用したのは瓦を重ねる形式でしたが、瓦にはそれぞれ微妙なアール(丸み)やゆがみなど一枚一枚にばらつきの違いがあり、それを7段、8段と積み重ねるにつれて、どうしても傾きや歪みが生じてしまいます。
一枚一枚を「どうやって組み合わせれば、全体として美しいラインが出るか」を感覚的に見極めていく作業は、石積みとはまた異なる難しさがありました。
石であれば叩いて高さを微調整することも可能ですが、瓦はそうはいきません。そうした中、園芸高校の生徒さんたちも真剣に、試行錯誤を繰り返していました。
このような現場のなかで得られるものは、単なる技術だけではありません。名のある造園職人の技を間近で見て学び、話を交わすことができるのも、大きな刺激です。
また、自分たちが日頃あまり手を出さない作業に触れることで、改めて基本に立ち返ることができたり、逆に「自分はこんなこともできるようになっていたんだ」と、自信に変わることもあります。
今回の講習の模様は、「造園連新聞」にも掲載されました。
紙面には、協力してくれた生徒たちの活躍や、職人同士の真剣なやりとりなどが写真付きで紹介され、改めて「造園という仕事の奥深さ」や「日本庭園の継承における意義」を感じさせられました。
人の手で自然を形作り、美しさを表現していく。
それは単なる作業ではなく、日本文化の精神性を受け継ぐ行為でもあります。今回のステップアップ研修は、まさにそうした庭師としての「志」を確認する、貴重な時間となりました。