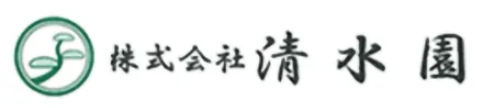vol.127 令和6年度 日本庭園管理士補ステップアップ研修【前編】
2025/7/21

ー前編ー 令和6年度日本庭園管理士補ステップアップ研修 〜技と感性を磨く現場から〜
皆様こんにちは。清水園でございます。
今回のコラムでは、「令和6年度 日本庭園管理士補ステップアップ研修」についてご報告させていただきます。
本コラムでもたびたび登場しております「日本庭園管理士」の資格ですが、受験資格の取得には定められた単位を修得する必要があります。単位そのものは講習や実習を通じて積み重ねるのですが、講習の多くが東京や奈良など遠方で行われるため、通常の業務と両立しながら参加するのはなかなか骨の折れることでもあります。
今年は、例年よりも参加者が少なく、9名という少数精鋭での実施となりました。しかしながら、東京の造園業者の方々や園芸高校の生徒さんたちの応援も得られ、総勢50名ほどの規模で研修を行うことができました。
当日は3つの班に分かれて作業が進められ、代表の班は「待合(まちあい)」と「うろこ垣」の制作を担当。
「待合」とは、主に茶庭(露地)に設けられる簡素な腰掛け場所で、茶室に入る前に客人が心を整えるための空間です。
「うろこ垣」はその名の通り、魚の鱗のように瓦を重ねて作る垣根で、滋賀県の寺下さんが考案したものです。通気性や採光性を保ちつつ、目隠しや風除けの役割も果たす意匠的にも美しい構造物です。
作業は思いのほかハードで、他班の取り組みを見学する余裕すらなく、ほぼ流れ作業のように進んでいきました。代表は「できれば2班が担当していた庭門の施工にも挑戦してみたかった」と、少し残念そうに話していました。
経験豊富な代表であっても、現場によっては初めての施工もあり、こうした実地研修の機会がいかに貴重であるかを改めて感じたようです。また、日本庭園管理士補には、可能な限り「人力での施工技術」が求められます。もちろん、現場では重機を使うこともありますが、すべての現場で使用できるとは限りません。とくに歴史的建造物の修復や保存地域の施工では、重機使用が制限される場合もあり、人の手による緻密な作業が必須となります。
庭づくりにおいて「人の手でどこまで美しく整えられるか」という感性と技術こそが、この資格に求められる本質なのかもしれません。