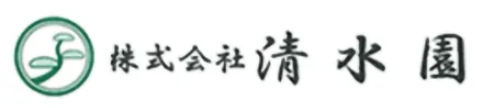vol.128 垣根工【前編】
2025/8/18

ー 前編 ー 垣根工の現在地 ー 鱗垣にみる技と継承
皆様こんにちは。清水園でございます。
今回のコラムでは、「垣根工(かきねこう)」をテーマに、お話させていただきます。
清水園でも時折、垣根を制作する機会はございますが、近年、造園業界で課題となっているのは、「きちんとした竹垣を作ったことのない職人」が日本全国に多く存在しているという現実です。
なかには、技能士の検定試験でしか竹垣を作ったことがない、という人も少なくありません。この問題は日本庭園士補の講習会やオンラインセミナーでもたびたび話題にあがっています。
清水園では、竹垣を制作する機会もあるため、ある程度の経験を積むことができます。
今回は、その中でも「鱗垣(うろこがき)」についてご紹介いたします。
もともと、片側が竹穂垣、もう片側が建仁寺垣だったものを、全面的に鱗垣に作り替えました。
特に大変だったのが、2トンほどある柱の建て入れ作業です。造園の現場では人力での重量物の運搬が意外とあります。周囲のものを傷つけず、かつ人力で安全に設置できるかが非常に重要です。そこに「建てる」と決めたならば、何としても成し遂げなければなりません。
垣根というものは、時の経過とともに必ず劣化・腐食していきます。そのため、定期的な作り替えが不可欠です。
伊勢神宮の式年遷宮のように、何度も作り替える中で技術を承継してきたのだと思いますが、現代では「壊すのはもったいない」との風潮があり、価格が高くても長持ちする塩ビ製の垣根を選ばれる方が増えているように感じます。
先日、京都を訪れましたが、格式高い料亭などでは今も竹垣が設えられており、文化を継承する姿勢が垣間見えました。
とはいえ、「垣根は腐らない方がよい」と考える方も多く、実際に制作する機会が減っていることから、技術の習得や継承が難しくなっていると感じます。
特に竹穂垣は、竹の揃え方や捌き方が難しく、やればやるほど手間がかかります。ある造園協会の方が「作れるのに作らない人が多い」とおっしゃっていましたが、その背景には、手間や費用の問題、メンテナンスの難しさがあり、庭師もお客様も敬遠しがちなのが現状です。
垣根を作り替える際、まずは解体作業から始まります。作るのには数日かかりますが、壊すのはわずか15〜20分ほど。
雪吊りや冬囲いなども同様ですが、あっという間に終わってしまう解体作業は、どこか切なさを伴います。
解体が終わると、次に柱を立てる作業に移ります。今回は立派な柱を使用し、コンパネの上にプラスチックボードを敷き、その上をパレットリフト(自動販売機などを運搬する台車)で慎重に運搬しました。
次に、チェーンブロックを用いて、高さ2m近い柱を50cm地中に埋め込みました。周囲には建物があり、ガラスや建物に傷を付けないように細心の注意を払いました。
チェーンブロックの作業では、吊るす対象物が機構の三角形の内側にしっかり収まっていないと、外側に力がかかりバランスを崩しやすいため、仮置きや吊り支点の微調整を繰り返しながら設置していきました。
柱は奥を高く、手前を低くする構造にしています。
続いて、柱が倒れないように、柱と柱の間に「ケミカルアンカー」で鉄筋を打ち込んで固定し、基礎部分にコンクリートを流し込みました。その上に基礎石と板石を設置して土台を整えます。
その後は瓦の設置作業へと移ります。瓦は一見すると同じ形に見えますが、実際には歪みやねじれがあり、重ねていくうちに微妙な高さのズレが出てしまいます。その傾きを整えながら重ねていくのが、非常に難しいポイントです。
こうした工程を経て完成した鱗垣ですが、魅力はその立体感と視覚効果にあります。角度によって見え方が異なり、ライトアップ時には裏側から光が透け、完全な遮蔽ではなく景観としても美しさを放ちます。
前編では、鱗垣の制作を通じて、垣根づくりの魅力や難しさについてお話させていただきました。
しかし、実際の現場では鱗垣だけでなく、さまざまな種類の垣根を求められることもあります。
続く後編では、別の施工主様宅で行った「格子垣・玉垣・四目垣」の作り替えについてご紹介いたします。