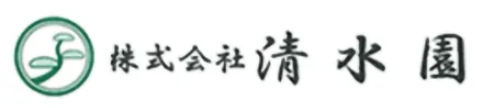vol.126 神様について【後編】
2025/7/7

―後編― 神様の存在と、命をつなぐかたち
倒れた場所を見た瞬間、「これは偶然ではない」と、代表も口にしました。そこには神様の存在を強く感じざるを得ない、不思議な“導き”がありました。そして、まるで誰にも迷惑をかけたくなかったかのように、静かに倒れていった御神木の心意気のようなものさえ感じたのです。
伐採後の御神木は、そのまま処分するにはあまりにも惜しい、美しく貴重な材でした。しかし、直径が細いため、板材としての加工には向かず、私たちは「薪として活かす」という選択をしました。
そこで話にあがったのが、志賀神社で毎年行われている「どんと祭」。どんと祭とは、毎年1月14日に行われる小正月の伝統行事であり、仙台市内の各地の神社で、お正月飾りやお守り、古神札などを焼納する神事です。この火祭りにおいて、御神木を少しずつ薪として焚き上げることで、その命を無駄にせず、祈りの場へと還していくことになりました。これから数年をかけて、大切に燃やされていく予定です。
また、八坂神社の宮司さんからも、「この木をお守りに加工してはどうか」という提案をいただきました。私たちは一部を玉切りにしてお渡しし、今後の活用をお願いすることになりました。
たとえ倒れてしまった木であっても、その命を次へとつなげていく方法はあります。御神木はこれから、薪として人々を温めたり、お守りとして誰かの心に寄り添ったりしながら、別のかたちで生き続けていくのです。
今回の出来事は、私たちにとって「神様とは何か」を改めて考えるきっかけとなりました。
自然の力により起こった出来事の中に、どこか人知を超えた何かが介在しているような、そんな感覚を抱くことができたことに、感謝の気持ちでいっぱいです。
自然を敬い、神様を想い、そして今ある命を大切にすること。
それは私たち造園屋にとっても、これからの生き方を見つめ直す大きなヒントになったように思います。
次回のコラムでも、自然とともに歩む私たちの仕事や、そこで感じたことをお届けしてまいります。どうぞお楽しみに。