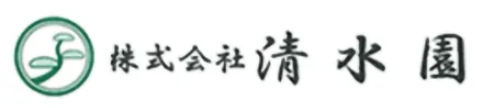vol.124 いろいろな伐採
2025/5/26

皆様こんにちは。清水園でございます。
本日お伝えして参りますのは、’ いろいろな伐採’についての内容です。
これまでの伐採作業では、作業員が木に登り、他の人達が地上で支えるスタイルが一般的でした。今回は、機械を使ったいろいろな伐採についてご紹介します。
まず、森林と里山の違いについて簡単にご説明します。
森林は自然のまま育つ場所ですが、里山は人が手入れをしなければ荒れてしまいます。
「山が荒れる」というのは、木が増えすぎて光が届かず、木々が弱っていく状態を指します。さらに木の根が弱ると、土砂崩れが起きる危険も高まります。
材木として使うためには、まっすぐな木を育てる必要があります。そのため、木を密集させて植え、上からの光だけが当たるように管理します。しかし、林業の衰退により手入れされない山が増え、荒れてしまっている場所も多くなっています。
今回作業したのは、ゴルフ場の風通しを良くするための伐採でした。
木を3分の1ほど間引き(不要な木を切ること)し、光と風が通りやすくなるようにしました。
伐採作業では、まず「残したい木」や「育てていきたい木」を選び、それ以外を切っていきます。
最初に、地面に広がる笹の葉や細い木を刈り払い、枯れている木や不要な木を伐採。全体のバランスを見ながら仕上げます。伐りすぎると景色が寂しくなってしまい、日当たりが良くなり今度は草が生えてきてしまうので、どれだけ木を残すか、そのバランスがとても大切です。
切った木は、そのまま放置せず、チェンソーで適度な長さに切って現地に集積し重ねておきます。こうすることで、山の中も歩きやすくなります。
続いて、道路沿いに立っていた高さ20メートルほどの枯れ木の伐採についてです。
今回は、ラフター(正式には「ラフテレーンクレーン」)を使いました。
ラフターとは、四輪駆動で荒れた地面も走行できる、作業現場用の移動式クレーンのことで、高所作業や重いものの吊り上げに特化した、大型の機械です。
今回使用したのは、25トンラフター。このラフターのすごいところは、機械との距離にもよりますが、1回あたり約1.5トンもある大きく長い木を一発で吊り上げながら切れることです。
通常なら細かく切り分けなければならない作業も、ラフターを使うことで、1日かかる作業がわずか1時間で完了します。効率も安全性も大きく向上します。
なお、ラフターを使用するには、現場にある程度広さが必要です。
狭い場所では、手作業による積み込み作業が必要になり、大きな労力がかかることもあります。
伐採した木は、「ヒヤブ車(専用の運搬車)」で集めて運びます。
ヒヤブ車は、アームの先端で木を掴み、トラックに積み込める仕組みになっており、大きな木も素早く運搬できます。
ふた掴みで2トンダンプがいっぱいになるほど、作業効率が高いです。
また、現場にウインチ付きの重機(小型のショベルカーのような機械)が入れる場合も、作業が楽になります。
コンマ1(3トン級の重機)を使って、人の力では運べない大きな木をウィンチで引っ張り倒したり、機械の近くまで引っ張って、ダンプカーに積み込みもできます。
木は、いずれ必ず伐採する時が来ます。
ただし、今は建物や道路が密集しているため、昔のように自由に倒せるわけではなく、周囲に被害が出ないように慎重な作業が求められます。
伐採は「一撃必殺」。一度でも方向を誤ると大事故になるため、プロでも最大限の注意を払って取り組んでいます。
また、伐採の仕事は木を切るだけでは成り立ちません。
伐採の計画、作業方法、人員確保、ラフターやヒヤブ車の手配、ごみの片付け、木の搬出など、現場全体の段取りがとても大切です。清水園では、これらすべてを自社でしっかりコーディネートできる体制を整えています。
ちなみに、代表は伐採作業が一番好きとのこと。
木を倒す前におとずれる不安感と木が倒れる瞬間の迫力と安堵感、作業が完了したときの達成感は、伐採でしか味わえない特別なものだそうです。







作業状況

作業状況


作業状況