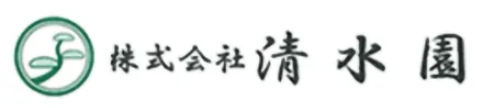vol.121 青葉区K邸 伐採・芝張替え
2025/4/14

皆様こんにちは。清水園でございます。
本日お伝えして参りますのは、’ 青葉区K邸 伐採・芝張替え’についての内容です。
施主様邸は、およそ200坪ほどあるお家で、ご要望はお庭の芝生を張り替えたいということと、ワンちゃんを自由に走り回らせたいのですっきりさせたいとのことでした。そこで、2度に分けて施工を行いました。
まずは、木を何本か伐採し、広範囲の草を枯らすところから始めました。その後、施主様からの要望で、愛犬が木々の下に入り込んでいなくなるのを防ぐために、低木は全て取り除くことになりました。
木々も、刈り込みで生い茂っていたので、もとの形に戻すために剪定を行いました。
芝生を張る際にもっとも重要なことは、もとの草の根っこを枯らすことです。そうしなければ、芝生の下からすぐに雑草が生えてきて草との戦いになるので、最初のやり始めが肝心です。一番早いのは、雑草の根っこを除草剤で枯らしてしまうことですが、その際に木々を枯らさないようにしなければなりません。
もとあった材料(木々や石などの素材)については、捨てるとお金がかかってしまうので、どこかで再利用できないかを常に考えながら作業をしています。今回の施工では、最初の工程で木々を伐採した際に掘って出てきた石は、庭の植栽の縁石代わりに並べ、再利用しました。植栽のきわに石を置くことで、お庭の景観が良くなったり、土留めができたりというメリットだけでなく、芝刈りの際にどこまで刈るのかの目安にもなります。
芝張りをする際は、もとの地盤の高さがあるので、好き勝手に盛ったり、削ったりということはできません。穴を掘って平にしてしまうことは簡単ですが、どうしても既存の木が何本か残るので、その木の根っこの地盤の高さは変えられません。そこで、その高さを生かしつつ、水がたまらないような地形の変化を考えることが重要です。
芝生は、まっすぐ平らな地形よりも、入り込みや高さのバランスなどの地形の変化があると、遠くから見た際に面白みが出るので、地形の変化をどうつけるかという感覚も大切になってきます。ただし、地形の変化がある芝生の場合には、刈りづらいというデメリットがあります。
芝生を刈るタイミングは、10日に1回程度で、2〜3cmの長さに留めておく必要があります。葉っぱの部分を刈れば、葉っぱの部分から新たな葉っぱが生えてくるのですが、長くなりすぎると、軸刈りといって葉っぱではない部分を切ってしまうので、枯れたような色になり、汚くなってしまいます。
最後に、隣のお家からの視線が気になるとのことでしたので、何もなかったところに植栽を植えました。目隠しの用途で植える際には、細い小さな木をたくさん植えることで、木々同士の間の隙間を少なくし、植栽が成長したときに一気に目隠しの役割を果たします。
また、落葉樹、常緑樹、落葉樹というように交互に植えていくと、まとまりが良くなります。落葉樹と常緑樹の違いは,葉の無い時期がある(落葉樹)のか緑の葉が常にある(常緑樹)のかです。
落葉樹は伸びるのが早いので、日陰を作りますが、冬は葉っぱが落ちてしまうので、窓の正面の木々は常緑樹である必要があります。
現在はあまり使われていない言葉ですが、日本のお庭には「役木」と言って、いろいろな役割の木がありました。現在でも残っているのは、家にくっついている「家付きの木」で、家に夏の直射日光が当たらないようにするという役割で植えられていました。
芝張りにおいても、他の作業においても、ざっくりとした施主様のご要望を受けた際に、完成後のお庭の状態が想像できるか否かが職人としての力量が問われるところです。「それならこういう風にしたら良いよ」と提案ができるのとできないのとでは大きな差です。とは言え、造園の仕事は自然物との戦いなので、図面があってないようなものです。作り始めに書いた図面とは全く違うものができるということは多々あります。難しくもありますが、それが面白いところでもあると感じます。