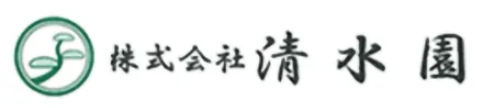東北福祉大学・ステーションキャンパスにおきまして、新しく駅が創設されるにあたり通学路を拡張する……というお話からはじまり、道路を拡張し石積みで終わる予定だったとの事。ですが隣のお家の擁壁に石積みを繋げていく途中に「畑も作るから。」との鶴の一声があり、畑への通路も作ることになったという現場。通路も作りながら、草刈りも行い…法面も作りながら、植栽も行い…様々な工程を同時進行で進めて参ります。
繁りすぎていた木に関しては伐採・処分したのですが…チッパーという機械を用いてチップにし、法面の植栽と竹の間に入れるなどして、フィルター代わりに使用しております。また、丸太状にし階段として再利用するなど、環境へ配慮しながら施工を進めて参ります。‘自然との共存’という意識は、造園家ならではなのかもしれません。

歩くのもギリギリな場所で どうなるものなのか思っていました。

解体屋さんが頑張ってコンクリートを解体し思った以上に広くなりました。

石積みし植栽をしました。

階段を撤去し擁壁をカッターで低くし重機で解体を始めます。

擁壁が無くなり石積みも低くなったので圧迫感が無くなりました。

入り口の高い石積みは垂直に積まず少し寝かした事により圧迫感をやわらげ入りやすくしました。

樹木も大きくなり石もさび色になり落ち着きが出てきました。



石積が大体終わり山砂を集め法面を仕上げました。

底部は板で法面の土の流出を防止し上部は植栽をしました。

石積み途中でこちらに繋ぐ通路を作るように言われ予定変更になりました。

緩やかではありますが法面です。

通路と上部に畑を開墾し簡易的に土留めをしました。

緩やかですが何も通路も無い状態です。どのように通路を作るか悩みどころです。

通路が出来ました。簡易的に竹で土留めをしましたが、竹が腐るころにはいずれ根が張り固まることでしょう。

ここに来る通路が狭いので仮置き場に大型ダンプで砕石を運搬し そこから3tダンプに積み替え運搬し地盤を固めて行きます。

重機で転圧と敷均しをしていきます。

石積の前にU字溝の高さを出し GLを決めていきます。

一番下場の所から石積みを始めます。 ブロックに並べる場合は隙間や勾配を合わせないと違和感が出ます。

石積が高くなる場合はセットバックし積む場合もあります。

石が積み終わり法面を整形していきます。

入り口の反対側も積んで行きますが、ブロックの継ぎ目は気を使います。

通路を積んでしまうと重機が出れなくなるので 終わるまで開けておきます。

上部の整地が終わり重機を出したので 入り口を積み始めます。

通路幅が決まり植栽をし通路を整形していきます。

石積み上部の植栽をしていきます。

法面下部を板で固め法面の土の流出を防ぎ植栽します。

植栽が終わり作業終了のはずでした。

平らな部分を開墾し畑になるように 石や根を撤去していきます。

耕運機で土をやわらかく耕運していきます。

まず法面の草や木など刈払い地盤を出して削っていきます。

法面の勾配が変わるので板で補強をし法面を削って勾配を変えていきます。

大きな重機を出してしまった後の追加工事でしたが 通路を広く取れないので小さな重機で開墾し通路を作っていきます。

刈り取った草や根や切り開いた枝等がかなり出ます。

削った土を盛り法面を整地して通路を作って行きます。重機が小さいので届かない部分は人力で叩いて固めます。

板で補強し法面を作って行きます。

上段畑の通路も切り開き開墾していきます。

通路と法面が出来て来ました。

落下防止の柵の杭を打ち通路と法面の仕上げをしていきます。

茂った樹木を伐採し空間を空け 日当たりを良くしていきます。

伐採した枝や葉などはチップにし通路に敷き詰めます。それによりゴミではなく肥料になり土に返していくリサイクルになります。

法面に杭を打ち割った竹で土留めをします。 割り竹はある程度曲がるので山道には便利です。裏込めにはチップや割り竹などを入れ 砕石の代わりにして土の流出を防ぎます。

法面に植栽し法面を固めていきます。

太い幹は階段の土留めに使用し なるべくゴミにしないように再利用を考えるのも 植木屋の仕事です。

丸太の階段が完成しました。山道はコンクリート資材より自然資材の方が落ち着きます。

通路の裏面と入り口を積んで終了です。