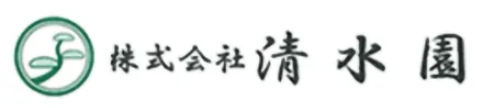地域によって数は異なりますが、東北六県の多くでは冬になると木の上に縄の傘をさしているような ’雪吊’ が見受けられます。
「基本的に雪吊りというのは、雪の重みで枝が折れないようにする為のものなのですが、縄でさまざま形の表現を変えることもできますので、中には装飾的な雪吊というのも存在します。清水園のある宮城は雪が少ないので、実用的なものと装飾的なもの両方ございますが、お隣の山形県などは雪が多いので実用的なものがほとんどです。形も異なりますし、場合によっては板で囲ったり…というものもございます。」
どれが良くどれが駄目という決まりはないものの、だからこそ個人における美意識が強く反映される’雪吊’や’冬囲い’。木々や現場に合わせ工夫を凝らすことで、冬景色が作られているのです。

全長13mのボンデンに 124本の荒縄で雪吊をしています。



松上部にボンデンを 乗せた固定し88本で吊っています。

4寸竹に48本で吊っています。 周りには竹を5等分に割った竹を各所に結束し 全体的に吊っています

樹高4m松に24本で 割り竹を回し全体的に吊っています。

こちらは曲がっている松なので 枝や幹を全体的に支えられる 様に要所要所に結んで支えています。 ボンデン上部飾りは一番シンプルな飾りです。

ボンデン飾りがワラボッチの例になります。

雪吊をする際まず支える柱を竹にするか、 丸太にするか決定し、 その後長さを決め縄を無駄のないまた、 短くならないように作って行きます。

上部で縄をまとめ、縄が 抜けたりしないように結束していきます。 飾りは決まりはないので自由ですが、かなり個人差があり、見て回ると楽しい物です。

上部飾りが半分完成です。

さらにもう一段飾りつけを施していきます。

上部飾りがおわったので、 縄を31本束に配分して行きます。 なお飾り結びは、立てる前に したほうが、触ったりしないのでいいと思います。

縄の配分が終わりました。

小さい樹木のボンデン飾りの例です。

小さい樹木のボンデン飾り の例です。

小さい樹木のボンデン飾り の例です。


13mの丸太に4gの縄が16玉使用しているので、大体200kgぐらいあるので、 人力で移動するのはとても大変です。

目的地に着きましたらクレーンでぶつからないように慎重に吊上げていきます。

真っ直ぐに持ち上がりとりあえず一安心です。

その次は真っ直ぐに立て込み結束し固定していきます。

柱の下部も動かないように杭を打ち込み結束して固定していきます。

柱の固定が終了したら今度は結束部に向かって縄を投げて行きます。 風がふいていたり、障害物が あると、投げづらいので大変な作業です。

縄を受け取ったら、今度は結ぶ場所に配置していきます。

振り分けが終了したら今度は縄を引っ張りながら結束していきます。

幹の部分には虫取りの為と防寒のためにワラを巻いています。 装飾の部分が強いので、キレイに巻いていきます。こちらは2段巻の例です。

5段巻のワラ巻き飾り結びが梅結びになります。

2段巻飾り結びは松結びです。

2段巻飾り結び笹結びです。

1段巻飾り結びは垣根結び3段です。

根巻する際はこちらの木の 場合かなりの太さになので、あらかじめワラを置いて準備します。 また地面に直接置くとわらが、汚れるので、養生して作業します。

普通はやらない工程ですが、上が太く結び目が上にずり上がるので、下巻をしています。

ワラを播き結束していきますが、結び目があまり上になると ワラが固定されないのでキチンと締まるように締め付けていきます。

時にはワラを叩きつぶしてさらに絞って固定します。

ワラが巻き終わり飾り結びを編み込んでいきます。

最後に飾り結びをして終了です。